|
【6】「各人の納付税額」の計算 |
|
「各人の算出税額」に、加算の規定と、税額控除の規定を適用して、それぞれの納付する税額を算出します。 |
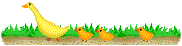 |
 |
「相続税額の2割加算」...{配偶者、1親等の血族(代襲相続人)}以外の者が、遺産を取得した場合に、適用されます。 |
 |
「贈与税額控除」...相続開始前3年以内に、贈与により、取得していた分について、相続税として、課税のやり直しをします。贈与により取得した財産の課税価格を相続財産に含める分、既に、贈与税として、納付した税額を、控除します。 |
 |
「配偶者軽減」...配偶者が、遺産を取得した場合には、法定相続分(法定相続分が1億6千万円に満たないときは、1億6千万円)までに相当する税額を、軽減する規定です。 |
 |
そのほか、「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」などの税額控除の規定があります。 |