|
【財産評価って...】 |
|
相続税・贈与税を計算するにあたり、金銭は、もらった金額そのものが、
財産の価額ということになりますが、資産をもらった場合は、
「その財産の価額は、いくらなの」という問題が、でてきます。
これを定めているの が、「財産評価基本通達」というものです。
詳細は、 国税庁のホームページ
の「通達等」>「法令解釈通達(基本通達)」>「財産評価」
で確認することができます。 ここでは、シミュレーションをご利用いただくにあたって、
「相続税の課税価格」や「贈与によって取得した財産の価額」を入力するための、
めやすになる情報として、おもなものだけ、簡略して、説明します。 |
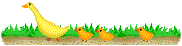
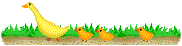 |
|
【土地及び土地の上に存する権利】 |
|
◇共通事項◇ |
 評価上の区分 評価上の区分 |
課税時期の現況によって判定した地目別に評価します。
ただし、一体として利用されている一団の土地が、2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、
そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとします。
地目には、宅地、田、畑、山林、雑種地等があり、その判定は、「不動産登記事務取扱手続準則」に
準じて行います。
固定資産評価証明書や登記謄本にも記載されていますが、
現況が異なる場合は、現況により判定します。 |
 評価単位 評価単位 |
利用の単位(「1画地」と呼びます。)ごとに評価します。
参照→
国税庁のホームページ |
 共有財産 共有財産 |
共有財産の持分の価額は、
その共有となっている財産全体を1つの財産として評価し、その価額を、
その共有者の持分に応じてあん分した価額が、
共有者の個々の持ち分についての評価額となります。 |
 財産評価基準書 財産評価基準書 |
財産評価で必要となる、路線価、倍率、各種割合、
地区区分等は、「財産評価基準書」に記載されています。
「財産評価基準書」は、各税務署に、その税務署を管轄している国税局管内のものは、
設置されています。その他の地区については、
各国税局と、管内に何ヶ所かの税務署等に設置されています。 |
|
◇宅地及び宅地の上に存する権利◇ |
 評価の方式 評価の方式 |
(1)路線価方式
(2)倍率方式
評価したい土地が、どちらの方式によるかは、「財産評価基準書」に記載されています。
|
 倍率方式 倍率方式 |
固定資産税評価額 x 倍率 ....「自用地価額」
「固定資産税評価額」は、「固定資産税評価証明書」に記載されています。
「固定資産税評価証明書」は市町村役場で入手できます。
「倍率」は、上記の、税務署等に設置されている、
「財産評価基準書」に記載されています。 |
 路線価方式 路線価方式 |
〔評価額〕
自用地の価額(/㎡) x 地積 ....「自用地価額」
「自用地の価額(/㎡)」は、その土地の形状により、接する路線の路線価をもとに、
一定の手順により算出します。
地積は、登記上の地積ではなく、課税時期における実際の面積です。
〔一方のみが路面に接する宅地の自用地価額〕
路線価 x 奥行価格補正率 ....(A)
「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線
(不特定多数の者の通行の用に供されている道路)ごとに設定されています。
「奥行価格補正率」とは、その宅地の奥行距離に応じて、
「奥行価格補正率表」に定める補正率です。
奥行距離は、原則として、正面路線に対し垂直的な奥行距離によりますが、
奥行が一様でない場合には、平均的な奥行距離によって算定します。
〔正面と側方に路線がある宅地(「角地」)の自用地価額〕
(A) + 側方路線価 × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率 ....(B)
路線価x奥行価格補正率 が高い路線が、正面で他方が、側方となります。
「側方路線影響加算率」は、地区区分ごとに定められています。
〔正面と裏面に路線がある宅地の自用地価額〕
(A) + 裏面路線価 × 奥行価格補正率 × 二方路線影響加算率 ....(C)
路線価x奥行価格補正率 が高い路線が、正面で他方が、裏面側方となります。
「二方路線影響加算率」も、地区区分ごとに定められています。
〔三方又は四方に路線がある宅地の自用地価額〕
(A)、(B)、(C)を併用して、算出します。
〔その他の補正〕
上記で算出した評価額に、さらにその宅地の状況に応じて、「不整形地」
「無道路地」「間口狭小または奥行長大」「がけ地等」などの補正を行います。
|
 貸宅地・借地権 貸宅地・借地権 |
貸宅地の評価 = 自用地価額 - 借地権(※)
※ 借地権 = 自用地価格 x 借地権割合
「借地権割合」は、その宅地の存する地域について定められています。
借地権の取引慣行がない地域においては借地権の価額は評価しませんので
貸宅地の評価 =自用地価額 x 80%
となります。
|
 貸家建付地・借家人の権利 貸家建付地・借家人の権利 |
貸家建付地の評価 = 自用地価額 - 借家人の権利(※)
※ 借家人の権利 = 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
「借地権割合」は、借地権の取引慣行がない地域においては、
20%として、計算します。
「借家権割合」は、その宅地の存する地域について定められています。
借家権の取引慣行がない地域においては、「借家人の権利」は、評価しません。
|
 豆知識 豆知識 |
一般的なめやす
路線価 = 時価の8割
固定資産評価額 = 時価の7割
時価 = 公示価格 / 0.8
おすすめサイト
タビスランド/税務解説集/路線価図の見方
|
|
◇農地◇ |
 分類 分類 |
(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地周辺農地
(4)市街地農地
農地を評価する場合、その農地を、上記に掲げる農地のいずれかに分類し、
以下の評価方法によって評価します。
上記の農地の種類は、「農地法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、
「都市計画法」ごとに、 それぞれの種類に該当する農地が、
定められています。[財産評価基本通達34(注)]
|
 純農地・中間農地 純農地・中間農地 |
固定資産税評価額 x 倍率
「固定資産税評価額」は、「固定資産税評価証明書」に記載されています。
「固定資産税評価証明書」は市町村役場で入手できます。
「倍率」は、上記の、税務署等に設置されている、
「財産評価基準書」に記載されています。 |
 市街地農地 市街地農地 |
〔比準方式〕
(宅地であるとした場合の価額(/㎡)※ - 造成費(/㎡))x 地積....(D)
※ 付近の宅地1㎡当たりの価額 x その農地と宅地との較差割合
「造成費(/㎡)」は、上記の、税務署等に設置されている、
「財産評価基準書」に記載されています。
〔倍率方式〕....倍率が定められている地域
固定資産税評価額 x 倍率....(E)
市街地農地のうち、「財産評価基準書」に倍率が定められている地域については、
倍率方式により、評価することができます。
「固定資産税評価額」は、「固定資産税評価証明書」に記載されています。
「固定資産税評価証明書」は市町村役場で入手できます。
「倍率」は、上記の、税務署等に設置されている、
「財産評価基準書」に記載されています。 |
 市街地周辺農地 市街地周辺農地 |
〔比準方式〕
(D) x 80/100
〔倍率方式〕....倍率が定められている地域
(E) x 80/100
|
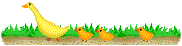
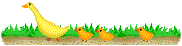 |
|
【家屋及び家屋の上に存する権利】 |
|
◇家屋◇ |
 評価単位 評価単位 |
家屋は、原則として、1棟ごとに評価します。 |
 評価額 評価額 |
固定資産税評価額 x 1.0
「固定資産税評価額」は、「固定資産税評価証明書」に記載されています。
「固定資産税評価証明書」は市町村役場で入手できます。 |
|
◇附属設備等◇ |
 家屋と構造上一体 家屋と構造上一体 |
家屋の価額に含めて評価するため、個別には、評価しません。
例えば、家屋の所有者が有する電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、
電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。)、ガス設備、衛生設備、
給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、
その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、
個別の評価はしません。 |
 門、塀等 門、塀等 |
再建築価額 - 経過年数に応ずる減価の額
再建築価額とは、課税時期においてその財産を新たに建築又は設備するために要する
費用の額の合計額をいいます。 |
 庭園設備 庭園設備 |
調達価額 x 70/100
調達価額とは、課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合
の価額をいいます。 |
|
◇貸家・借家権◇ |
 評価額 評価額 |
貸家の評価 = 家屋の評価額 - 借家権(※)
※ 借家権 = 家屋の評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合
「借家権割合」は、その宅地の存する地域について定められています。
借家権の取引慣行がない地域においては、「借家権」は、評価しません。 |
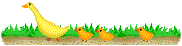
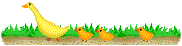 |
|
【その他のおもな財産】 |
|
◇構築物◇ |
 評価単位 評価単位 |
1個の構築物ごとに評価します。ただし、2個以上の構築物で、
分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものは、
それらを一括して評価します。 |
 評価額 評価額 |
( 再建築価額 - 減価の額※ ) x 70/100
※ 取得の時期から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額
又は減価の額
この場合の償却方法は定率法によるものとし、
その耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
に規定する耐用年数によります。 |
|
◇一般の動産◇ |
 評価単位 評価単位 |
1個又は1組ごとに評価します。ただし、
1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、一括して一世帯ごとに
評価することができます。 |
 評価額 評価額 |
〔原則〕
調達価額に相当する金額
〔調達価額が明らかでない動産〕
同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額 - 減価の額(※1)
※1 取得の時から課税時期までの期間(※2)の償却費の額の合計額又は減価の額
※2 その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とする。
この場合の償却方法は定率法によるものとし、
その耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
に規定する耐用年数によります。 |
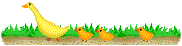
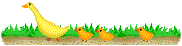 |
|
【みなし財産】 |
|
◇生命保険金等◇ |
 みなし財産となる場合 みなし財産となる場合 |
被相続人(亡くなった方)の死亡により、生命保険契約の保険金や、
損害保険契約の保険金を取得した場合に、それらの保険金のうち、
被相続人が保険料を負担した分相当分につき、相続税の対象となります。 |
 課税財産の金額 課税財産の金額 |
取得した保険金 x ( 被相続人が負担した保険料 / 払込保険料の全額※ )
※ 被相続人の死亡の時までに払い込まれたもの |
 非課税金額 非課税金額 |
〔非課税限度額〕
500万円 x 法定相続人の数
〔非課税限度額以下〕
相続人の取得した生命保険金等の合計額が、上記、生命保険金等の非課税限度額以下
である場合には、相続人の取得した生命保険金等の全額が、非課税となります。
〔非課税限度額をこえる〕
相続人の取得した生命保険金等の合計額が、上記、生命保険金等の非課税限度額を
こえる場合には、各相続人につき、次の金額が、非課税となります。
非課税限度額 x ( A / B )
A = その相続人が取得した生命保険金等の合計額
B = すべての相続人の取得した生命保険金等の合計額
|
|
◇退職手当金等◇ |
 みなし財産となる場合 みなし財産となる場合 |
被相続人(亡くなった方)の死亡により、その被相続人に支給されるべきであった
退職手当金等で、その死亡後3年以内に支給が確定したもの、の支給を受けた場合に、
相続税の課税対象となります。 |
 課税財産の金額 課税財産の金額 |
一時金で支給...... 退職手当金等の金額
有期定期金で支給.... 支給総額 x 支給期間に応ずる割合※
終身定期金で支給.... 支給年額 x 受取人の年齢に応ずる倍数※
※ いずれも、相続税法第24条に規定されています。 |
 非課税金額 非課税金額 |
〔非課税限度額〕
500万円 x 法定相続人の数
〔非課税限度額以下〕
相続人の取得した退職手当金等の合計額が、上記、退職手当金等の非課税限度額以下
である場合には、相続人の取得した退職手当金等の全額が、非課税となります。
〔非課税限度額をこえる〕
相続人の取得した退職手当金等の合計額が、上記、退職手当金等の非課税限度額を
こえる場合には、各相続人につき、次の金額が、非課税となります。
非課税限度額 x ( A / B )
A = その相続人が取得した退職手当金等の合計額
B = すべての相続人の取得した退職手当金等の合計額
|
|
◇用語の意味◇ |
 法定相続人 法定相続人 |
「法定相続人」とは、相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます。 |
 法定相続人 法定相続人 |
「法定相続人の数」とは、上記の「法定相続人」の人数ということになりますが、
相続人の中に、養子がある場合、「法定相続人の数」に算入する養子の数は、
次の人数までとなります。
被相続人に実子がいる場合....1人
被相続人に実子がいない場合...2人 |
 養子 養子 |
養子のうち、次の養子は、上記「法定相続人の数」における、
人数の制限を受けません。
(イ)特別養子縁組による養子となった者
(ロ)被相続人の配偶者の実子で、その被相続人の養子となった者
(ハ)被相続人との婚姻前に、配偶者の特別養子縁組による養子となった者で
婚姻後にその被相続人の養子となった者
(ニ)実子または、養子の代襲相続人となったその者の直系卑属
|
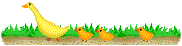
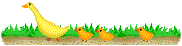 |
|
【ご案内】 |
 |
シミュレーションをご利用いただく上で、財産評価がネックとなって、
相続税・贈与税の財産価格(課税価格)の入力ができない場合は、
お気軽にお問い合わせください。 |